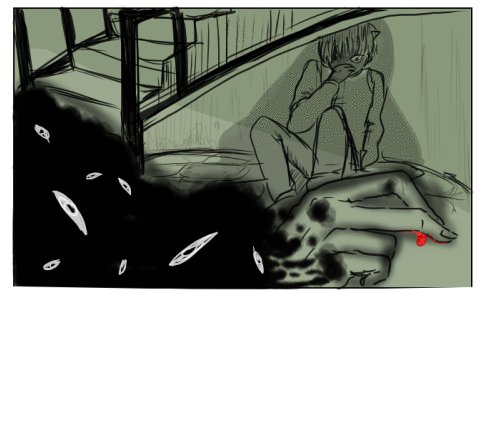※ハートフル嘔吐ストーリー。ばっちいです注意。
先程剥いたばかりの大根の皮を今度はおもむろに千切りにしはじめたものだから、閻魔はつい口を挟んでしまった。彼は生ゴミ相手に一体何をしているのか。
「…トドメでもさしてるの?」
コンロの上では鍋がコトコトと煮えていて、少し甘い出汁の香りがキッチンに立ち込めている。出汁なんて味の素で十分なのでは、と閻魔なんかは思うのだが、なんでも数時間前から昆布を水に浸すだけで、それはそれは素晴らしい出汁がとれるそうだ。わざわざ手間をかける鬼男が妙に楽しそうなので、普段は何も言わずに見守るだけなのだが今日は好奇心がそそられた。
「いえ、勿体無いからきんぴらにしようと思って。っていうか、トドメってどんな思想してるんだお前…」
「きんぴらに?牛蒡も人参もないのに?大根の皮を?まっさかー、また私を嵌めようっていうんでしょ」
「お前がいつも勝手に嵌っているんだろ。あんたみたいに立派な出自の人は知らないでしょうけど、大抵のものはごま油と鷹の爪で炒めるときんぴらになるんですよ」
りっぱなしゅつじ、頬袋の中で反芻して笑い出しそうになった。彼は些か私に夢を見すぎている、と閻魔は密かに思う。なるほど鬼に比べれば立派な存在に見えるのかもしれないが、十王や他の神々との会議でどれほど自分の出自が蔑まれていることか。閻魔は自然と湧いてでてきた自虐思考を慌てて打ち消して、話に集中しようとした。それもできる限り人好きのいい笑顔を浮かべて、なるべく陽気そうに振る舞うよう心掛けた。恋人を不安にさせるのはあまり好ましくない。
「へえ、全然知らなかった。大根の皮も食べられるんだねえ」
「大根なんて葉の部分も炊き込みご飯にすればあますことなく食べられますからね。そういえばあんたは辛いのあんまり得意じゃないんでしたっけ」
「ううん、そうでもないよ。カレーだと子供用を所望したいくらいかな」
「…全然駄目じゃないですか。じゃあ、とりあえず鷹の爪は二つだけにしましょう」
閻魔ははあいと甘ったるく返事をして、鬼男の横顔を見つめる。火を扱っている彼はフライパンの上の出来事にすっかりお熱で、ちっとも閻魔に構ってくれない。それでも閻魔は飽きずに鬼男の横顔を見つめてみる。長い睫毛に均整のとれた鼻梁。少し俯くたびに月色の髪がさらさらと揺れる。彼が構ってくれるまで何千年だって飽きずに待てる気がした。恋の病はいつだって千年だの永遠だのと大袈裟な妄想を駆り立てるものだ。その大袈裟な年月の恐ろしさを実体験として知っている閻魔ですらこの有様なのだから、そのへんのインフルエンザよりもよほど恐ろしい。
「そんなに近くにいると油が跳ねますよ」
毎日煮え銅を飲まされている自分に今更火傷の心配なんて、とひねくれた反発が浮かんでくる。しかし、瞬きを三回繰り返す間に、大人げある折り合いをつけた。鬼男くんなのだからしょうがない。
「そうだねえ、ちゅーしてくれたらどいてあげようかな」
「…馬鹿じゃねえの」
鬼男は眉を思い切り寄せる。閻魔はその怖い顔は照れているだけだと知っていたので、瞼を閉じて恋人を待った。そのうち震えた柔らかい唇が押し付けられる。付き合ってからそこそこの歳月が経つというのに、いつまでたっても慣れない初心さは閻魔の心をくすぐった。
「子供じゃないんですから、火の傍でふざけちゃだめですよ」
見え見えの照れ隠しに耐えかねて閻魔は笑ってしまった。鬼男もまた照れ臭そうに笑った。
「いただきます」
その日の夜は素晴らしい食事だった。蛍烏賊と大根の煮物に件の大根の皮のきんぴらと生姜焼きに真っ白なご飯と味噌汁。閻魔は鬼男と食事をとるたびに、絵に描いたような幸せな光景に目が眩む。おそるおそる熱い味噌汁を口に含むと、麹のなんともいえない香りがした。愛おしげに自分を見つめる鬼男にぎこちなく微笑みを返す。いつだって、肯定的な言葉というのはどうにも照れ臭いものだ。
「おいしいよ」
鬼男は当然ですと腕を組んだ。その顔にはたしかに誇らしさが浮かんでいて、閻魔はおいしいよ以外にも言えたらもっと喜ばせてあげられるんだけどなあ、と途方に暮れた。
「それにしても、僕がこんなに天才的に料理がうまいっていうのに、あんたは全然食べませんねえ。ごはんのおかわりもあるのに」
「元々食が細いし、むしろ私が食べてるだけでもすごいことだよ。おいしくなかったら食べもしないもの」
「そんなんだから鶏ガラみたいな体してるんですよ」
「う、うるさいなー!筋肉がなんぼのもんじゃい!この筋肉鬼男!筋男!」
夕食の後は歯磨きをして、お互いを舐めたり噛んだりする行為を軽く楽しんでから寝た。鬼男が寝たのを見計らって閻魔はベッドを抜け出す。ギシ、とベッドのスプリングが大きく軋んだのでヒヤヒヤした。念の為、掌を彼の瞼の上にかざして、眠りをより深いものへと誘う。掌の気配を察したのか、彼の髪の色と同じ色の艶やかな睫毛が僅かに震えた。
「おやすみなさい」
鬼とは思えない美しい姿をした青年のことを閻魔は心底愛おしいと思う。
「…っとと、もう限界だ」
閻魔はそう独りごちると、手を腹のあたりに添えながらよろよろと歩き出す。震える体に鞭を打って廊下の外までなんとか抜け出すと、欲望に耐えかねてうずくまった。口をきつく閉じようとするが間に合わない。うぐえ、という醜い音が口から漏れた。吐瀉物がビチャビチャと音をたてて廊下の大理石を汚す。
「あらら、間に合わなかったかあ…」
絵に描いたような幸せは所詮絵でしかなく、閻魔の身体はたしかに死んでいて、本当のところ、心臓すらもろくに動いてはいない。つまるところ、食事なんてできないのだ。咀嚼したものは胃袋に詰まるだけ詰まって、どこにも行くことがない。鬼男はそれを知らない。知られたくない、と閻魔が願う限り彼がこの事実を知ることはないだろう。秘密は閻魔の得意分野だし、鬼男は人の裏を覗き見るのが苦手だ。
「うっ…げぇ…」
消化できない異物を体は容赦無く排出しようとする。受け入れることはしないくせに、吐き出す行為は得意なあたり自分の肉体らしいと閻魔は自嘲気味に笑う。
「はぁっ…はっ…」
先程の幸せな香りなんてどこへ消えたのか。今となっては饐えた臭いだけが残る。吐瀉物のなかから先程褒めたばかりの味噌汁の具のようなものを発見して、閻魔はまた会ったねとつまらない冗談を零した。食後はいつだって最悪な気分だが、消化されない魚の骨がたまに胃袋を破ることもあるので、それを思うと今日の夕飯はまだマシな方だ。胃液が他の臓器を溶かしていく感覚はそう好ましいものじゃない。閻魔は震える手を冷たい大理石の上に置いた。
「ぁっ…」
えずくのがやまない。胃が痙攣するたび情けない声が漏れる。それでも、と閻魔は涙で霞んだ視界で考える。
それでも。
「今日のオヤツはロールケーキですよ」
「やったあ!ロールケーキ!私すきなんだよねえ」
卵色のいかにも柔らかそうな生地に真っ白なクリームが包まれているのを見て、閻魔は喉元まで胃液がせり上がってくるのを感じた。昨日のキスを待つ時のように瞼を閉じて、覚悟を決める。まるで祈りのように。
「…あんた存外柔らかい食べ物すきですよね。年寄りみてえ」
「あー、ひどいなあ。いいじゃん。ふわふわしたのが好きなんだよ」
数時間後には吐瀉物になっているだろうかたまりに向かって閻魔はフォークを突き立てた。お飾りの苺が潰れる様はどうしようもなく滑稽で、なぜだか自分を思い起こさせる。
「うん、おいしいよ」
今日も恋人に向かって閻魔はそう微笑み返す。おいしいよ以外にも言える言葉があったらいいのになあ、と今日も閻魔は途方に暮れる。味というものを判別できたのは一体何万年前のことだったかしら、閻魔は瞼を閉じながら遥か昔に思いを馳せた。
O_A_A
(150512)未来のない味蕾。